Netflixで独占配信をされている大人気ドラマ「愛の不時着」。
ハリウッドレベルの海外戦略を仕込んでいるスタジオドラゴンが手掛けていることもあり、世界で人気を博しているようです。
今回は愛の不時着でリ・ジョンヒョク(ヒョンビン)の親の役職「総政治局長」について紹介します。
Netflixで愛の不時着を見る
総政治局長は内閣官房長官のようなNo.2的存在
まず、北朝鮮は総書記をトップとして、その下に総政治局、総参謀部、人民武力省の3組織があります。
パワーバランスはその時々の政権や情勢にもよるそうですが、現在は「総政治局」が圧倒的に強いそうです。
役割としては、軍の政治査察を担う機関、要するに軍部の人事権・検閲権を握り、国への忠誠を管理する機関のトップらしいです。
日本でいうと全く同じような役割はありませんが、かんたんにいうと内閣総理大臣がNo1、その次官である内閣官房長官が総政治局長のような存在といえそうだと思います。総政治局長は軍の監視や人事権を握っているため、劇中でも出てくる軍事長官は支配下にあるみたいですね。
それでは、この記事は以上です。
Netflixで愛の不時着を見る
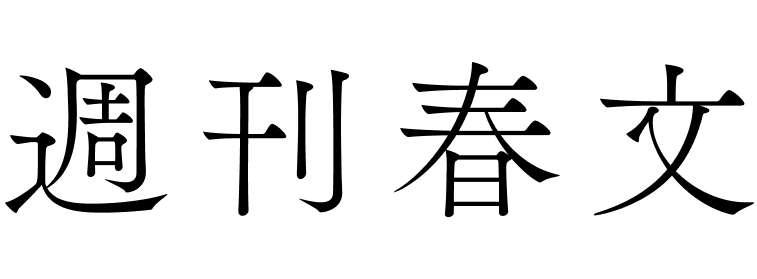



















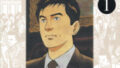





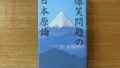





コメント